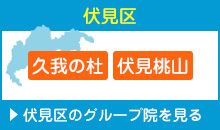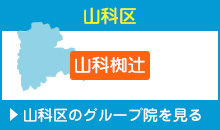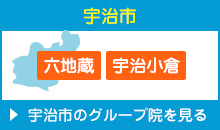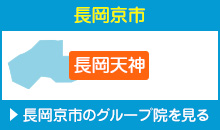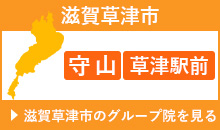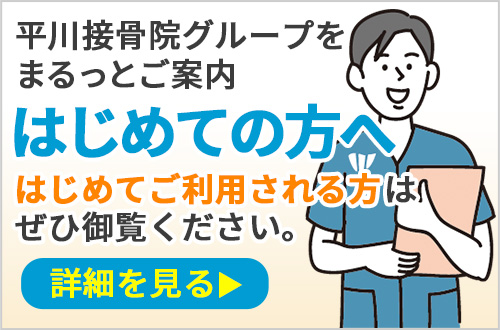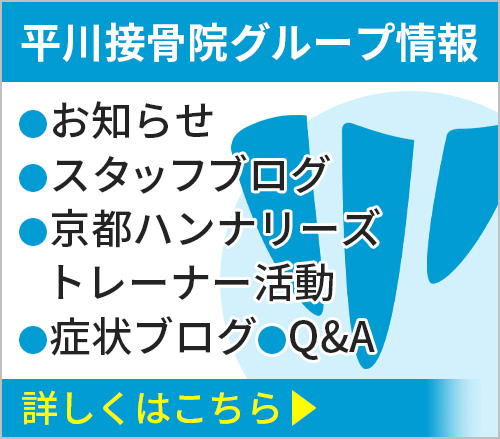肩こりってどういう状態?
肩こりというのは病名ではなく症状の一つです。特に日本での有訴者率では男性では2位、女性では1位という結果で多くの方が症状を訴えておられます。
(平成22年国民生活基礎調査より)
肩こりの原因として一番大きく関係してくるのが血流です。
筋肉は周りの毛細血管から酸素や栄養素を供給されることで柔軟性のある良い状態を保っています。
しかし、同じ姿勢が続くデスクワークや運転では腕や頭をさえる為に筋肉にはずっと力が入った状態になってしまいます。
その力が入った筋肉が周りの毛細血管を圧迫してしまい血流が悪くなった結果、筋肉が酸欠状態・栄養不足状態になり硬い筋肉になってしまいます。
そして怠さやこり感、終いには発痛物質が産生されて痛みを感じてしまうのです。(=トリガ-ポイント)
なぜ利き手ではない方の肩がこるの?
みなさんも疑問に思われている利き手とは反対側の肩のこり。
実はここにも血流が関係しています。
普段の生活を思い返してみて下さい。買い物、料理、通勤。。。
利き手は品を選ぶ、かき混ぜる、定期を取ったりスマホを触ったりなど細かい動きをしたいので常に動かしている状態です。
しかし、利き手と反対側の手はどうでしょう。
買い物カゴを持つ、フライパンやお鍋を持つ、鞄を持つのは利き手と逆ではないですか?
実は利き手と反対の手というのは力仕事や支えていることが多くなります。
特に物を持つ時(肩をすくめる動作)や頭を支える時には僧帽筋という肩に付いている大きな筋肉に力が入ります。

上記でも述べたように、この僧帽筋という筋肉にずっと力が入っていると周りの毛細血管を圧迫し、血流が悪くなってしまいます。
そして筋肉は同じ姿勢を20分続けていると硬くなるという性質もあるため、20分鞄や買い物袋を下げているとあっという間に筋肉は固くなってしまいます。
また、筋肉にはポンプ作用があるため、動かしている方が血流は良いのです。
冬場、利き手と反対側の手は冷たくないですか?
このように、利き手と反対側の手(腕)は動かすことも減ってしまうため血流が悪くなるのです。
肩こりをしっかりと治すためには?
肩こりをしっかりと治すためには血流を促すことが一番です!!
血流を促すことで発痛物質や老廃物が流れていきます。
また、筋肉が柔らかくなるために必要な酸素や栄養素も供給されるので、筋肉が柔らかい柔軟性のある状態に戻ることができます。
まとめ
利き手とは反対側で肩がこる理由がお分かり頂けたかと思います。
普段何気なくしている作業や動作が肩こりの原因になることが多いので、こまめに動かし血流を改善させることを意識してみて下さい。
肩こりも放っておくと頭痛や歯痛、手の痺れの原因になりますので、早めに予防・対処するように心がけましょう!